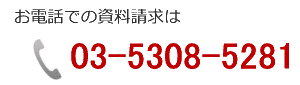ラーニングスペース
LERNING SPACE
★ 2025年「新入社員の傾向」と「新入社員研修のポイント」

今年の新入社員研修
「今年の新入社員の傾向について知りたい」という相談を受けることが増えている。新入社員の特徴を理解することは、新入社員教育を行う上で不可欠である。実際、近年の社会や価値観の変化は急速であり、その影響は新入社員の思考や行動にも色濃く現れている。本記事では、「2025年新入社員の傾向」と「新入社員研修のポイント」について詳しく解説する。この10年で社会は劇的に変化した。多様性、デジタル化、ハラスメント、働き方改革、ワークライフバランス、メンタルヘルスなどが、新入社員の考え方に大きな影響を与えている。企業の研修担当者は、自社の新入社員教育を見直し、改善点がないかを確認しながら読んでいただきたい。

新入社員研修の一覧を見る
社会人としての考え方やビジネスマナーを学び、スムーズに職場に適応するための教育プログラムです。
1.10年間の社会の変化について
この10年間で起きた社会の価値観の変容は非常に大きい。新入社員教育について考える前に、この10年間で起きた価値観の主な変容について、整理しておこう。
尚、ここでは、あくまでも企業サイドから見た人材育成という点で、近年の価値観の変容が及ぼす課題についても触れながら解説を進める。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)やパワーハラスメント(パワハラ)に対する意識運動があった。
パワハラについては、基準は存在するものの、相手の感じ方によるところも大きく、判断が難しいケースも多い。その結果、上司がパワハラを過剰に意識するようになり、指導をためらい、部下育成に支障が出るといった現象も多くの企業で見られるようになった。
セクハラについては、浸透した結果「会社の人間には恋愛感情を抱かない」という考えが広まりつつある。この傾向は、恋愛関係だけでなく、社内で友人を作ることすら避ける風潮にも発展している。「仕事とプライベートを分ける」と考える社員は増えている。
ハラスメント意識の向上やコンプライアンスの重視は、職場環境の健全化や公平性の向上に寄与している。一方で、社員は日常の言動に慎重にならざるを得なくなっているのは事実である。結果、こうした取り組みが社員間の信頼関係やコミュニケーションを希薄にしている側面もある。したがって、コミュニケーション重視の企業は、独自の対策を取る必要がある。
性別、国籍、年齢、LGBTQなど、多様な背景を持つ人々の存在を認め、受け入れる社会への転換。LGBTQに関しては、オリンピック競技への参加、トイレ使用の問題など、多くの課題が残されている。
働き方改革は、長時間労働の是正や柔軟な働き方を通じて、労働環境の改善と生産性向上を目指す取り組みである。企業にとって、従業員満足度の向上や優秀な人材の確保、離職率の低下といったメリットがあると謳われている。しかし、新入社員がやりがいを求めて離職する傾向もあり、これが新たな課題として浮上している。テレワークに関しては、社員間のコミュニケーション不足が生産性低下の一因となるとの指摘もある。また、労働時間短縮は生産量の低下や人材不足をさらに悪化させ、企業の労働力確保が困難になるリスクも大きい。
精神的な健康を重視する風潮が強まり、カウンセリングやセルフケアの需要が増加。働きすぎやパワハラへの意識も高まる。
SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルといったキーワードが普及し、環境保護や持続可能性が個人や企業の価値観に浸透。
会社への帰属意識よりもキャリア形成を優先する思考である。特に、若い世代においては、会社に対するロイヤリティが希薄で、キャリアの選択肢として転職が優先される傾向が強まっている。企業側としては、長期的な人材育成が困難になり、社員のスキルや経験を活かした成長を促進することが難しくなる。キャリア形成重視の考え方も、近年のメディアの影響は大きい。本来、キャリアは仕事の経験値において積みあがるものである。したがって、会社への貢献度とキャリア形成は、同一のベクトルになることが多い。会社への帰属意識が仕事に対するモチベーションを高め、キャリア形成を加速させると考える方が自然である。業界を渡り歩いていけるほどのキャリアを積みげるには、真剣に仕事と向き合うことが大前提である。そして、仕事に真剣に向き合うためには、それなりの会社へのロイヤリティも軽視できないだろう。
2.社会の価値観と会社の価値観のすり合わせが必要
★ 社会の価値観は常に変化する
社会の価値観を理解することは重要だが、それをそのまま企業の価値観とする必要はない。なぜなら、社会の価値観の変容は全てが企業発展のためのものでもなく、永続的なものでもないからである。社会の価値感は、常に変化する。したがって、社会の動向を理解しつつ、自社のモラルや方針を明確に確立することが重要である。もちろん、コンプライアンスを守ることは前提であるが。
価値観の変化は予想以上に早い。昭和時代の企業優位の価値観から令和の個人優位へと移り変わり、さらに次の価値観が数年内に浮上する可能性もある。今の価値観も定着するものと、新たな価値観に取って代わられるものがあるだろう。たとえば、LGBTQへの推進運動は大きいが、課題も多い。
また、ワークライフバランスも社会的には推奨されているが、全ての企業が同じ方針を取る必要はない。企業が「社員には一生懸命働いて成長してほしい」と考えるなら、それを明確に示すべきである。たとえば「ワークライフバランスを否定はしないが、当社は努力を評価し、成長できる環境を提供する」と表明するのも一つの方法だ。
重要なのは、企業としての価値観や方針を明確にすることである。パワハラ、LGBTQ、多様性、ワークライフバランスに関する考え方は、経営層だけでなく、管理職や社員全体で合意形成を図ることが不可欠である。その上で、企業の方針を一貫して実行することが求められるのである。
社会は常に最良の価値観を提供しているわけではない。それは、戦争に突き進んでいった熱狂を考えればすぐにわかる。企業としては、社員の成長や幸福、そして企業発展のために、どのように人材育成を行うべきかを、冷静に組み立てることが大切ではないだろうか。
3.【2025年度】新入社員の傾向について
最近の新入社員の傾向、社会的価値観、学校教育、家庭教育などから、「2025年新入社員の傾向」について言及したものである。入社してから慌てることのないように、今から傾向を読み、準備しておくと良い。
3-1. 理不尽さに慣れていない
最近の若者は、理不尽な状況に直面する機会が少なく、耐性が低い傾向がある。時に、「理不尽」と感じられる状況は、立場や考え方の違いから生じている場合も多い。ある事象に対して、理不尽と決めつけることで、思考停止になり対話や問題解決の機会を逃してしまうことがある。新入社員においては、「理不尽さ」について、あらかじめ心の準備をしておくことで、心理的な躓きを防ぐことができる。
3-2. 個人主義的思考が強い
プライベートを優先的に考える傾向が強い。精神的な負担が大きいと感じた場合、退職を選ぶことも珍しくない。この背景には、近年の社会的な価値観の変化や風潮が大きく影響している(ライフワークバランス、キャリア志向、メンタルヘルス重視など)。この考え方には、個人の幸福や健康を守るというメリットがある一方で、仕事に対する意識が薄く、キャリア形成や課題解決の力が育ちにくいというデメリットもある。こうした特徴を踏まえ、個人の価値観を尊重しながらも、成長につながるサポートを行うことが重要。
3-3.キャリア志向が強く、会社に対するロイヤリティが低い
「キャリア志向が強い」というのは、単に仕事中心であるという意味ではなく、むしろ「会社に所属することへの反発からたどり着いた意味合い」で使われることが多い。実際のところ、転職市場で優位に立てるようなキャリア形成は、真剣に仕事に取り組まない限り得られない。真剣に仕事に取り組む中で、実は会社に対する帰属意識がモチベーションを維持するために重要であることが分かる。本来であれば、会社に対するロイヤリティを高めることが、仕事へのモチベーションを高め、さらにはキャリア形成にもつながるという順番が理想的である。会社が仕事を学ぶ場であるからこそ、この点は自然に理解できる。
3-4. 指示待ち傾向が強い
指示待ち傾向は、数年前から新入社員に多く見られる特徴のひとつだ。周囲と協調意識が強く、目立つことを嫌う傾向にある。仮に高い意欲を持っていたとしても、それを周囲に悟られることは快く思わない若者が増えている。このような傾向は、自己主張が弱いことや、リスクを避ける姿勢から来ている場合が多い。指示待ちの姿勢が続くと、自分で考え行動する能力が育ちにくく、結果的に仕事の効率や成長に限界が生じることがある。そのため、上司や先輩は積極的に自発的な行動を促し、部下が自信を持って判断を下せるようにサポートすることが求められる。
3-5. デジタルネイティブである
最近の新入社員の傾向として、デジタルネイティブであることが挙げられる。スマートフォンやSNSが当たり前の環境で育ち、デジタルツールに対する抵抗が少なく、オンラインコミュニケーションやクラウドサービスの利用に長けている。しかし、対面でのコミュニケーションや細やかな配慮が求められる場面では、不安を感じることもあるため、バランスの取れたスキルの習得が重要。また、SNSの活用については、気を付ける点について事例を用いた勉強会なども必要である。
3-6. 「家庭と学校」と「社会人」の乖離が大きい
近年の学校生活では上下関係が薄くなり、先生と生徒、上級生と下級生という間柄も以前と比べてフラットな関係性になっている。一部の体育会の学生を除けば、挨拶や敬語も身近なものではなくなりつつある。また、学校生活では競争をさせない主義が強くなり、競うことへの嫌悪感を持っている若者も少なくない。家庭教育においても、礼儀や挨拶をしっかりと教えるということも少なくなっている。社会人としての基礎的な教育がまったくなされていない状態で入ってくる新入社員も少なくない。
4.2025年新入社員研修のポイント
2025年度の新入社員研修はビジネスマナー等の基本項目の他に、下記のテーマを中心に置き、広い視野を養い、仕事への意識と会社への帰属意識を高める内容とすることを薦める。
4-1 社会人としての基本を丁寧に教える
家庭や学校で礼儀や挨拶を教えることが殆どなくなり、上下関係の経験を持たない新入社員が増えている。したがって、新入社員研修では、より丁寧に礼儀や挨拶、言葉遣いの必要性を説き、実践出来るようにトレーニングすることが求められる。礼儀や挨拶、返事、言葉遣いは、社会においては人間性への判断材料になることも、伝えていきたい。
さらに、電話応対や名刺交換についても、時間を取ってレクチャーしていく必要がある。電話応対については、家庭で電話機に触れたことのない新入社員も多い。
4-2 会社組織への理解を深める
会社は単なる個人の集まりではなく、チームとして協力し成果を追求する組織であることを新入社員に認識させることが重要である。役職や部署ごとに明確な役割があり、業務フローが有機的に連携することで目標が達成されるという組織の仕組みを理解させる必要がある。また、報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の徹底や、ルールとマナーを守る姿勢が信頼関係の基盤となることも強調すべきである。個人の自由な発想が重要視される時代であっても、組織が機能するためには協調性と責任感が不可欠であり、この意識を持つことが組織人としての第一歩となる。
4-3 上司の役割を認識する
パワハラに対する社会的意識の高まりは望ましい傾向である一方で、企業現場では上司がハラスメントを恐れるあまり、部下指導を避ける問題が生じている。また、新入社員の中にはパワハラに対して過剰な意識を持ち、正当な注意でさえパワハラと捉え騒ぎ立てる例も少なくない。このような状況を踏まえ、新入社員研修において上司の役割について明確に伝えることが、現代の企業では不可欠である。上司は部下の成長を促す責任を担い、ときに注意や叱責を通じて指導を行う役割を持つことを、新入社員に理解させる必要がある。また、パワハラと指導の境界を会社として明確に示し、周知徹底することも重要である。
4-4 会社に対するロイヤリティについて学ぶ
キャリア志向が重視される現代の社会では、そのような考えを持って入社する新入社員も少なくない。しかし、会社での業務に真剣に向き合わなければ、転職を含めたキャリア形成は実現し得ない。キャリアを築くためには、まず目の前の仕事に没頭し、経験を積むことが重要である。それを支えるのが、会社に対する帰属意識であり、モチベーションの向上にもつながる。生涯一つの企業で働けと言っているわけではない。所属する会社においては常に帰属意識を持つことが、質の高い仕事とキャリアアップの基盤となる。この考え方を新入社員にしっかりと伝えることが求められる。
4-5 仕事に対する意識について学ぶ
ワークライフバランスの考え方が広く浸透したことで、定時で仕事を終え、プライベートを重視する若者が増えている。この発想自体は個人の自由であるが、企業においては仕事の成果が評価の基準となる点は変わらない。これは社会的風潮に左右されるものではない。しかし、新入社員の中には、ワークライフバランスの考え方こそが唯一正しい働き方であり、それに沿って業務を進めるべきだと誤解している者も少なくない。直接的な主張がなくとも、多かれ少なかれその影響を受けているのが現状である。したがって、新入社員研修の段階で、企業では成果が評価の基準であり、その成果を上げるためには努力と工夫が求められることを明確に伝える必要がある。
4-6 SNS利用の注意点を自覚する
SNSの利用に関しては、これまで社会問題となった具体的な投稿事例を取り上げながら、リスクや影響についてしっかりとレクチャーすることが重要である。例えば、企業秘密の漏洩や誤解を招く表現、プライバシー侵害に繋がる投稿が、どのようなトラブルや信用失墜を引き起こしたのかを具体的に示すと効果的である。講義形式にとどまらず、受講後には学んだ内容を基にしたレポートの提出や、事例を元にしたグループディスカッションを実施することで、企業人として許されない投稿についての理解を深め、より強い意識を持たせることができる。SNS利用のリスク管理は、現代において欠かせない社会人基礎力の一部であると認識させたい。
4-7 コミュニケーションの重要性を学ぶ
近年、仕事とプライベートを明確に分けて考える若者が増えている。職場を「仕事をするためだけの場」と割り切る傾向があり、その結果、職場の同僚とプライベートでの交流を避けるケースも少なくない。このような考えが広がると、社内の人間関係が希薄化し、組織全体の連携や成果に悪影響を及ぼす可能性がある。
仕事と人間関係は切り離して考えられるものではない。特にチームで業務を遂行する際には、良好な人間関係が構築されていることで、コミュニケーションが円滑になり、モチベーションの向上や成果の向上につながる。そのため、新入社員研修の段階で、職場における人間関係の重要性を伝え、適切なコミュニケーションスキルを身につけさせることが極めて重要である。
4-8 積極性を学ぶ
近年、新入社員の傾向として「指示待ち型」が目立つようになっている。この傾向の背景には、「失敗したくない」という心理的な抵抗が大きく影響している。そのため、新入社員研修の段階で、失敗に対する意識を変えることが重要である。
どのような行動にもリスクは伴う。しかし、リスクを恐れて自ら行動をためらっていては成長が望めない。企業としては、自ら考え、主体的に行動する人材を評価するという姿勢を明確に示すことが求められる。このメッセージを伝えることで、積極性を持って行動できる人材の育成につながるのである。
5.まとめ
新入社員研修カリキュラムを組む際に、「社会の価値観」と「会社の価値観」についてのすり合わせを行うことをお勧めしたい。定期的に価値観のズレがないか、あるとすれば会社の方針はどうしていくかを明確にすることで、社員の見えない不満感にも気が付くことができる。また、上司が部下に対してどのように接したらいいか、会社方針が明快であれば指導しやすい。
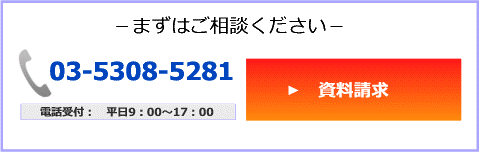
資料請求、お問い合わせ